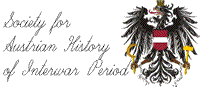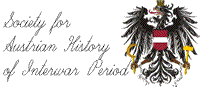ホロコースト(Holocaust)とは,第二次大戦時にナチス・ドイツによって行われたユダヤ人虐殺を表す言葉として広く使われている。ショアー,ジェノサイドという言葉が用いられることもある。
約600万人にも及ぶユダヤ人が,強制収容所で,栄養失調や病気のため,あるいはガス室にて死んでいった。
ホロコーストの犠牲者には,ユダヤ人だけでなく,共産主義者らの政治犯,シンティ・ロマ人,エホバの証人,同性愛者なども含まれる。
強制収容所は戦前から存在したが,絶滅を目的とした収容所が建設されるのは1942年以降のことである。絶滅収容所のなかでも,アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所はあまりにも有名である。
「アウシュヴィッツの嘘」を主張するホロコースト否認論も存在するが,“考える会”ではこの立場はとらない。

・ホロコーストは人類共通の問題だと考える。
・ホロコーストが行われていた当時,オーストリアはドイツ第三帝国の一部として加担していた。
・オーストリア内にも強制収容所が存在した。ヒトラーがその反ユダヤ主義を身に付けたとされるウィーンは,オーストリアの首都である。
・強制収容所の要職に“オーストリア人”が数多くついている。
・そもそもアドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler,1889/04/20-1945/04/30)自身が“オーストリア人”である。
他にも,
・アドルフ・O・アイヒマン
・エルンスト・カルテンブルンナー
・アルトゥル・ザイス=インクヴァルト らがいる。

某新聞に掲載されたある大学生の『シンドラーのリスト』についての投稿を紹介する。
→投稿: 「シンドラーのリストに感動」
(クリックすると,別のウィンドウで開きます。)
ここで触れられている「一つの生命を救う者が世界を救える」という言葉と,アドルフ・アイヒマンが残した「百人の死は悲劇だが百万人の死は統計だ」という言葉とを比べてみて欲しい。
その違いは歴然で,あまりに対照的である。
生命とは唯一つそこに存在するものであって,番号を付けてガス室で処理するものではないのだ。
彼,あるいは彼女はこの世にたった一人しかいない。
百万人の死は統計ではなく,百万人の人に係わったさらに多くの人々の哀しみなのである。
その一人の生命を救うのに尽力したのは,オスカー・シンドラー(Oskar Schindler,1908/04/28-1974/10/09)だけではない。
ここでは,2人の義人の名前をあげておこう。
・杉原 千畝
・ラウル・ワレンバーグ らがいる。

・歴史家論争
1986年6月,ベルリン自由大学教授のエルンスト・ノルテは『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙に「過ぎ去ろうとしない過去」と題された論説を発表した。それに対して哲学者ユルゲン・ハーバーマスが反論する形で始まったのが歴史家論争である。
この論争において大きな争点となったのは,ユダヤ人絶滅政策に代表されるナチスの犯罪は,歴史上に類を見ないものなのか,それともその他の残虐行為(例えばスターリンやポル・ポトによる虐殺)と比較可能なのか,ということであった。ノルテがナチスによるユダヤ人大量殺戮をスターリンの粛清といった類似の蛮行と比較することで弁明的に相対化して論じたのに対し,ハーバーマスはナチスの犯した行為への厳しい反省こそが西ドイツ(当時)の自由と民主主義の基礎となる,と述べている。歴史的な事象の比較は,それぞれの事象に対する考察を深めるためになされるものであって,どちらか一方の罪を取り除くためになされるべきではないだろう。
またこの論争は同時に,東西ドイツが分裂した状況(ここにオーストリアを加えることもできよう)で,ドイツ人は歴史の中にどのようなアイデンティティを求めるべきかが争われた論争でもあった。この点に関してユルゲン・コッカは「集団としてのアイデンティティへの希求が必ずしも民族(Nation)とか民族の歴史に向けら
れなくてはならないということはないのであって,むしろ,集団としてのアイデンティティには,もっと別の次元(地域的,ヨーロッパ的,宗派的,ヒューマニズム的など)が存在するのであり,民族的アイデンティティはその中のただの一つにすぎず,支配的ともいえないものでしかない」,と指摘している。

・ゴールドハーゲン論争
アメリカの政治学者ダニエル・ゴールドハーゲンが1996年に出版した『ヒトラーの意に喜んで従った死刑執行人達 -普通のドイツ人とホロコースト』をきっかけに生じた論争を指す。
ゴールドハーゲンの論旨の特徴は,ホロコーストに代表されるナチスの残虐行為を行ったのは狂信的なナチスだけではなく,著作の副題にもなっている「普通のドイツ人」も「自らの意志で」それに加わった,という所にある。学問的には杜撰な部分も多いこの著作に対し,新聞・雑誌を始め歴史家達はこぞって非難を浴びせたが,ゴールドハーゲンをむかえてドイツ各地で行われた公開討論会においては,聴衆は彼を圧倒的に支持したのである。
こうした論争の常として「勝者」を設定することは難しく,また無意味ではあるが,ゴールドハーゲン論争が再統一後のドイツにおいて,ナチスの過去とどのように向き合わなければならないか,という問いを「普通のドイツ人」に改めて問いなおしたことは評価されてしかるべきであろう。