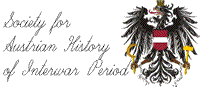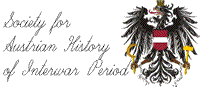アンシュルス期のオーストリア(1938.03〜1945.05)
オーストリア→1939 オストマルク→1940 オストマルク大管区→1942 アルプスとドナウ大管区
1939.04 9州⇒7大管区
ウィーン
下オーストリア
上オーストリア
ケルンテン
ザルツブルク
シュタイアーマルク
ティロール
フォラールベルク
ブルゲンラント |
 |
ウィーン
下ドナウ(+ブルゲンラント一部)
上ドナウ
ケルンテン
ザルツブルク
シュタイアーマルク(+ブルゲンラント一部)
ティロール(+フォラールベルク)
|
*基本的に伝統的州を温存
*オーストリアの名称の抹消 |
 |

- 非合法党員グループ(Leopold)
- ケルンテン派グループ(Klausner,Rainer,Globocnik)・・・最も成功
- 亡命者グループ(Franz Hofer)
*人事の基本政策・・・オーストリア・ナチスの古い指導者の排除
・各大管区の有力な地位(大管区指導者:ガウライターなど)に就任
・占領地域への派遣(特にバルカン地方)
・ドイツ本国(7%)よりも高いナチ党員の割合(10%)

・・・教育の世俗化,関連団体の解散,修道院・学校・教会の没収,世俗的利用,聖職者の収容所送り
◎オーストリア・ナチスの手で実行される
*アンシュルス以前からの反教権主義
←ドルフス・シュシュニク体制の擁護者としてのカトリック教会
反教権主義の中心・・・ウィーン,シュタイアーマルク,ケルンテン
| 1938.07 |
1934年の政教条約の撤回。 |
| 1938.08 |
市民婚の導入,離婚を公認。 |
| 1938.10 |
SAに援護されたヒトラー・ユーゲントのメンバーがウィーン大司教宅を襲撃。
翌週 反教会大集会で,ウィーン大司教の人形が縛り首にされる。
↑
多くのオーストリア人は,伝統的にまた基本的にローマ・カトリック教徒であり,これらの出来事に深い衝撃を受ける。 |

- 物価の上昇,賃金の低下,食糧不足→生活費の上昇
- 失業問題の解消・・・賃金格差
“失業はないが,バターもない”
- ドイツ本国,オーストリア間の経済格差
- 観光業への打撃・・・西部諸州
裕福なイギリス人,アメリカ人→ドイツの歓喜力行団(KDF)の行楽客

| 1938〜 |
非常に小規模で散発的だが存在
・オーストリア自由運動
・大オーストリア運動
・オットーネン
・オストフライ etc.
|
| 1941〜 |
組織的な抵抗グループの登場
・オーストリア闘争同盟
・オーストリア中央委員会
・・・上オーストリア,ザルツブルク,ティロールに至る情報網を組織。 |
| 1942後半〜 |
ゲリラ活動の展開
・・・シュタイアーマルク,ザルツブルク,上オーストリア,ケルンテン |
| 1943.01末 |
スターリングラード戦でドイツ軍敗北 |
| 〜1944夏 |
増加をたどる。オーストリアの独立を目指す
←モスクワ宣言(1943.11.1) |
| 1944.12 |
臨時オーストリア国民委員会(POEN)の結成 |
| 1945〜 |
国民的規模での展開 |
| 1945.03 |
05グループ・・・すべての抵抗組織を統合 |
| 1945.04〜05 |
上オーストリア,ザルツブルク,ティロールの州都では,
連合軍が到着する前に,抵抗グループが権力掌握
|
[抵抗運動の担い手]
- カトリック教会
- 君主主義者
- 学生,若者
- 共産党,R.S.(革命的社会主義派)
- 社会民主党−左派・右派
[抵抗運動の目標]
- 迫害されている人々,及び,逮捕・処刑された者の家族への援助
- 軍の士気の解体
- 不必要な犠牲の阻止
- ドイツの軍事的・行政的解体
- 早期停戦
- 抵抗運動の発展
- 連合国との接触
- ナチス崩壊後,政府を引き継ぐために必要な準備
- 自由で独立したオーストリアの回復